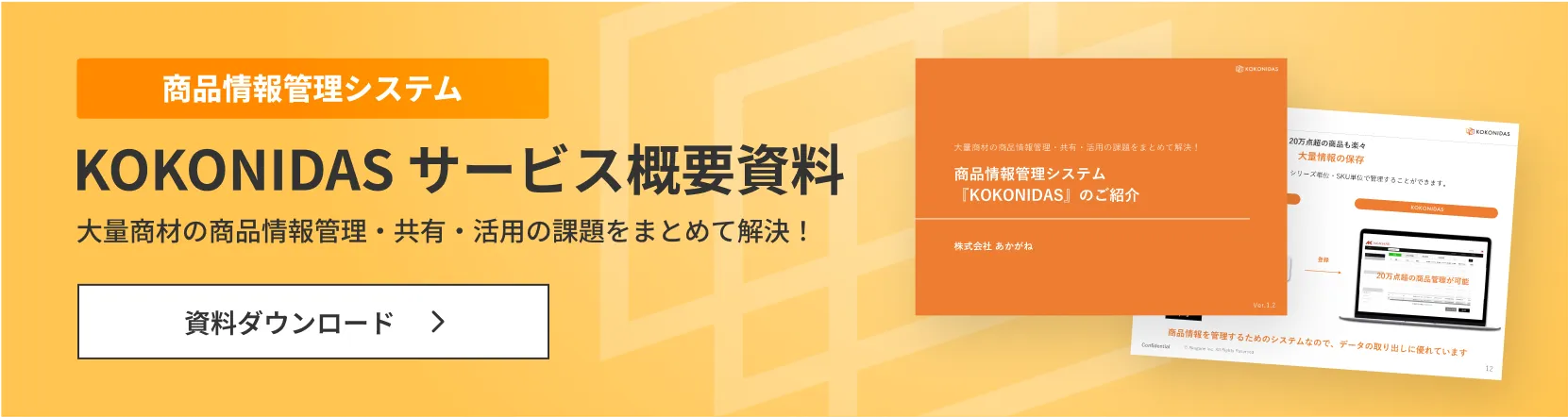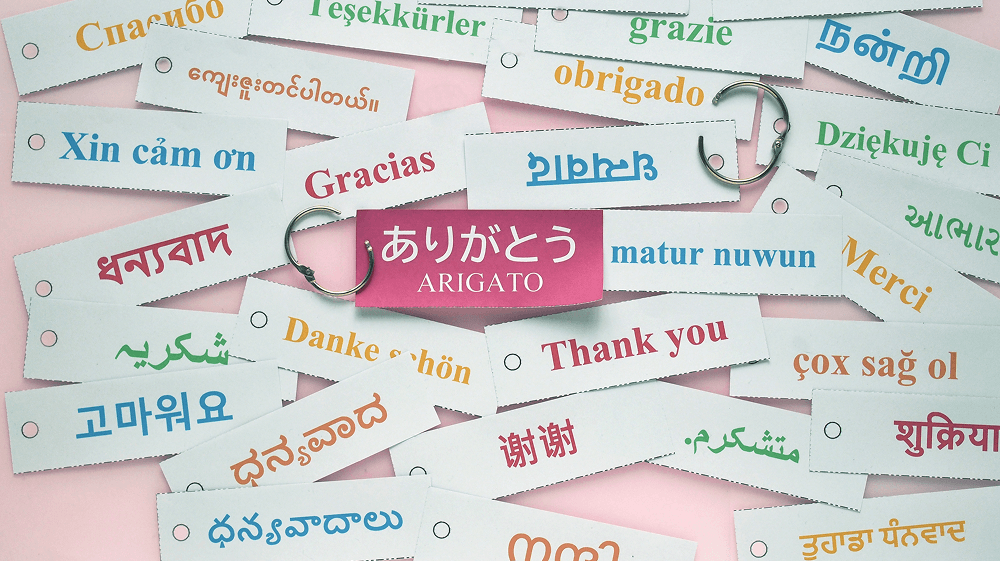記事公開日
最終更新日
部品管理システムとは?部品管理の重要性やシステムの選び方について解説

製造業において、生産に必要な部品のさまざまな情報を管理・活用する部品管理は重要な役割を持つ業務です。部品管理が適切に行われてこそ、安定的な生産を維持できるといえます。
ただ、部品点数が増えるほど部品管理業務は煩雑になるため、「部品管理が適切に行えず困っている」「部品管理を効率化できるシステムを導入したい」といった担当者の方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、そもそも部品管理とは何かや、重要性などを解説したのち、便利な部品管理システムの機能や選び方について解説します。部品管理の効率化に役立つ具体的なシステムも紹介するので、ぜひ最後までチェックしてみてください。
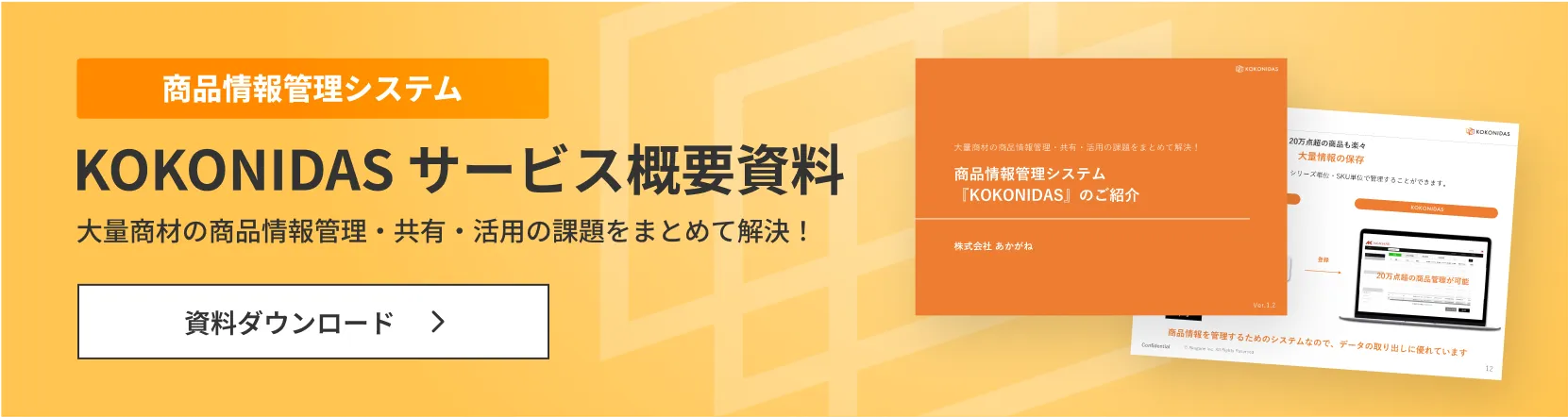
部品管理とは
部品管理とは、主に製造業において部品に関する情報を管理・活用することを目的として行う業務のことです。部品の在庫数量や保管場所の管理はもちろん、使用する製品・ロット番号・仕入先・保管期限・価格・画像や図面といった部品に関するさまざまな情報を管理します。
部品管理の重要性
部品管理の重要性についてチェックしておきましょう。
生産の安定性を支える
製造業において安定的な生産を続けるためには、適切な部品供給が必要不可欠です。生産に必要な部品が在庫切れを起こすと、生産ラインがストップして生産計画が崩壊します。適切な部品管理によって各部品の適正在庫を維持することは、生産の安定性を支える重要な業務だといえるでしょう。
コストの最適化に貢献する
部品管理が適切に行われていない場合、余計なコストが発生するリスクがあります。
必要以上に部品在庫が増える過剰在庫の状態になると、保管に必要なスペースが広くなります。倉庫などをレンタルしている場合は、倉庫使用費がかさむ可能性があるでしょう。
また、管理不足による部品の劣化や使用期限切れは、廃棄コスト増加の原因です。在庫数や保管場所が明確に管理されていない場合、誤発注による余計なコストが発生するケースもあります。
品質保証とトレーサビリティに役立つ
部品管理は、品質保証やトレーサビリティの観点でも重要です。例えば部品が原因の製品不良が発生した際、それがどのロットで、同じロットの部品がどの製品に使用されたかを追跡する必要があります。部品管理が適切でなければ、こうしたロットの追跡は困難です。
一方、部品管理が正しく行われていれば、原因追求・リコール対応・再発防止がスムーズに実施できるでしょう。
業務効率を向上させる
業務効率を向上させるためにも、適切な部品管理は欠かせません。部品の種類・在庫数量・保管場所が適切に管理されていなければ、生産に必要な部品を探したり、発注したりする際に余計な時間がかかります。
部品が適切に管理されていれば、誰でもすぐに必要な部品を探し出し、数量や状態を確認可能です。これは部品管理業務の属人化を防ぐ意味でも重要なポイントだといえるでしょう。
製造工程全体を最適化する
製造業では、購買・設計・製造・品質管理・営業などさまざまな部署が連携して業務を行います。部品管理は、各部署の連携を助け、製造工程全体を最適化するためにも重要な業務です。
例えば、部品管理が不適切だと、各部署の業務に以下のような悪影響が考えられます。
|
部署 |
不適切な部品管理による悪影響 |
|---|---|
|
購買 |
部品の在庫数量が把握できず適切な発注ができない |
|
設計 |
取り扱っている部品の情報が整理されておらず設計業務に活用できない |
|
製造 |
部品の在庫切れにより製造が滞る |
|
品質管理 |
製造不良があった際のリコール対応・原因調査・再発防止対策が滞る |
|
営業 |
製品供給が不安定になり適切な提案ができない |
部品表(BOM)とは
部品管理には部品表(BOM:Bill of Materials)が活用されます。BOMとは、ある製品の製造に必要な部品のリストのことです。BOMを見れば「この製品の完成にはどの部品がどの数量必要なのか」を理解することができます。
BOMに記載されている情報としては、以下のようなものが挙げられます。
|
項目 |
内容 |
|---|---|
|
製品番号 |
対象の製品の識別番号および製品名 |
|
部品番号 |
必要な部品の識別番号 |
|
部品名 |
必要な部品 |
|
必要数量 |
製造に必要な各部品の数 |
|
階層構造 |
部品を構成する部品、などの階層構造 |
|
使用用途 |
設計図のどの場所・機能に使われるのかの情報 |
|
単価・ |
部品の単価や仕入先 |
BOMは設計・製造部門だけでなく、購買・在庫管理・品質管理といった幅広い部門で活用されます。部品管理の精度・効率向上はもちろん、発注・組み立てミスの防止や製品のトレーサビリティ対応などに関わる重要な情報が部品表(BOM)です。
また、BOMは管理する情報や主な用途によって大きく4種類に分類される場合があります。
|
種類 |
用途 |
|---|---|
|
E-BOM |
製品設計に基づく構成の管理 |
|
M-BOM |
製造に使う構成の管理 |
|
P-BOM |
調達・購買に必要な構成の管理 |
|
S-BOM |
保守・アフターサービスに必要な構成の管理 |
部品管理(BOM)システムとは
部品管理(BOM)システムとは、製造に必要なすべての部品情報(BOM)を一元管理・活用するためのシステムのことです。手書きのリストやExcelへの手入力といった従来の方法が抱える以下のようなさまざまな課題を解決し、効率的な部品管理が可能となります。
|
従来の方法 |
部品管理(BOM) |
|---|---|
|
必要な部品情報を見るのに時間がかかる |
必要な部品情報にすぐアクセス可能 |
|
部品情報の変更・更新に |
必要な範囲の情報を |
|
部品情報が各部署に |
部品情報の |
|
管理業務が |
誰でも |
|
別のシステムとの |
別のシステムとの |
部品管理システムには、統合型部品管理システムと用途別部品管理システムの2種類があります。それぞれの特徴を確認しておきましょう。
統合型部品管理システム
統合型部品管理システムは、製品のライフサイクル全体を通じて1つのBOM情報を各部門で共通利用する方式・システムです。E-BOM(設計部品表)・M-BOM(製造部品表)・P-BOM(購買部品表)などを一元化したデータベースで統合的に管理します。
変更や更新がリアルタイムで反映されるため用途別部品管理(BOM)システムと比べると情報の一貫性が高く、各部門で同じ情報を個別管理する必要がない点がメリットです。開発・製造・保守まで全社的な最適化がしやすいのもポイントだといえます。
用途別部品管理システム
用途別部品管理システムは、各部門が自部門の目的に特化したBOMをそれぞれ独立して管理する方式・システムです。E-BOM(設計部品表)・M-BOM(製造部品表)・P-BOM(購買部品表)など、用途に応じて別の部品管理が行われます。
用途別部品管理システムのメリットは、管理方法の自由度が高く、部門の業務内容に合わせて柔軟な部品管理ができる点です。また、一度にすべての部品情報を統合する必要がないため、比較的導入しやすいでしょう。
ただし、各システム間の同期を適切に行わなければ、リアルタイムな情報管理ができません。また、同じ情報を部署ごとに管理する二重管理のリスクがある点にも注意が必要です。
部品管理システムでできること・機能
部品管理システムにできることや機能は、主に以下の7つです。
それぞれの機能をチェックしておきましょう。
部品情報の管理
部品情報の管理は、部品番号・品名・仕様・型番・単位・仕入先など、製品を構成するすべての部品情報を一元的に登録・整理・管理する機能です。部品ごとに図面や技術資料を添付することもでき、設計図やCADデータとの連携も可能です。
また、同一部品の重複登録を防いだり、廃番品や代替品の登録・管理も行えるため、設計や調達の業務ミスを未然に防げます。正確な情報を共有することで、設計・製造・購買・在庫といった各部門でのスムーズな業務連携が実現でき、製造の品質とスピードが大きく向上します。
部品情報の検索
部品情報の検索は、必要な部品を迅速かつ正確に見つけるための機能です。部品番号や名称、キーワードの検索はもちろん、材質やサイズなどの属性条件での絞り込み、使用している製品からの逆引き検索、部品図面や写真のプレビュー表示などにも対応しています。
これにより設計者は流用できる部品をすばやく特定でき、現場担当者は仕様確認や保管場所の把握がスムーズに行えます。検索精度とスピードが向上することで、情報収集にかかる時間や人的ミスが大幅に削減され、業務の効率化と標準化に大きく貢献します。
部品情報の更新
部品情報の更新は、部品の仕様変更や型番の切り替え、仕入先変更などの修正を正確かつ効率的に行うための機能です。変更履歴やリビジョン番号の管理に対応しており、いつ・誰が・どこを変更したのかを明確に記録できます。
また、変更が関連する製品や他の部品に影響する場合は、BOMへの自動反映も可能なため、情報の一貫性が保たれます。設計変更による手戻りや、現場・調達部門との情報ずれを防ぐことで、全体の生産性と品質を向上させることができます。
部品在庫管理
部品在庫管理は、各部品の在庫数や保管場所、入出庫履歴をリアルタイムで把握・管理する機能です。最低在庫数(発注点)の設定により在庫不足を自動で検知し、発注タイミングを逃しません。ロケーション管理によって「どこに何があるか」が一目で分かり、棚卸し作業も効率化されます。
また、ロット番号や有効期限などの属性も追跡できるため、トレーサビリティ対応や品質保証にも活用可能です。適正在庫を維持しながらも、無駄な在庫や欠品リスクを最小限に抑えることができます。
製品管理
製品管理(BOM管理)は、製品を構成するすべての部品やユニットの階層構造をツリー形式で管理する機能です。E-BOM(設計視点)・M-BOM(製造視点)・S-BOM(サービス視点)など、用途に応じたBOMも柔軟に対応可能です。
各部品の使用数量・構成レベル・設計変更の履歴なども一元的に管理でき、製品ごとの原価集計や構成比較にも活用できます。これにより、設計変更時の影響範囲の把握が容易になり、組立・製造現場での作業指示も正確かつスムーズに展開できるようになります。
アクセス権限管理
アクセス権限管理は、部品管理システム内の情報や機能を「誰が・どこまで扱えるか」を制御するための重要なセキュリティ機能です。ユーザーや部門ごとに、閲覧・編集・削除・承認などの操作権限を細かく設定できます。これにより、意図しない情報改変や誤操作、機密情報の漏洩を防ぐことが可能になります。
また、作業ログや操作履歴も記録されるため、「誰が・いつ・どの情報にアクセスしたか」が後から追跡でき、コンプライアンスやトレーサビリティの観点でも安心です。大規模な製造組織では特に不可欠な機能であり、全体の業務統制にも直結します。
外部システム連携
外部システム連携は、部品管理システムと他の業務システムとの間で情報をスムーズにやり取りするための機能です。
これにより、二重入力や伝達ミスを防ぎ、設計・製造・調達・会計といった全社的な業務をシームレスにつなぐことが可能になります。業務全体の最適化、リアルタイム情報共有、そして意思決定のスピードアップにも大きく貢献する重要な機能です。
部品管理システムの選び方
部品管理システム選びのポイントは、主に以下の7つです。
それぞれの選び方のポイントを押さえ、自社に適した部品管理システムを選択しましょう。
自社の課題を解決できる機能を持つものを選ぶ
導入する部品管理システムを検討するうえで大切なのは、自社の課題を解決できるシステムかどうかです。「なぜ導入するのか」「何を解決したいのか」という導入目的を明確にし、適した機能を備えた部品管理システムを選択しましょう。
多くの企業が、業務の属人化・設計変更時の情報伝達ミス・在庫の過不足・部品情報の散在など、さまざまな課題を抱えています。部品管理システムは、こうした問題を可視化し、改善するための手段ですが、目的が曖昧では適切なシステムを導入できません。
目的が明確であれば、自社にとって本当に必要な機能・操作性・予算感が明確になり、無駄なコストの増加も避けられます。システム選定の最初の一歩として、自社の業務課題と期待する効果をしっかり整理しましょう。
業種・業態に合った機能を備えたものを選ぶ
部品管理システムはすべての企業に共通する仕組みではなく、業種や製造形態ごとに必要とされる機能が大きく異なります。自社の業務に対応しやすい部品管理システムを選ばなければ、かえって業務効率が低下するリスクもあるため要注意です。
たとえば、頻繁な設計変更が発生する電機・精密機器業界では・バージョン管理・CAD連携・リビジョン履歴の保持などの機能が不可欠です。一方で、大型設備や重機を扱う業界では、製品単位での構成管理・製造工程に応じたM-BOM構成・サービスパーツの追跡などが重視されます。
ただし、多機能・高性能であればよいというわけではありません。ITリテラシーやリソースに限りがある場合は、操作の簡単さや学習コストの低さ、導入コストの低さが重視される場合もあるでしょう。業種・業態に合った機能を確認しつつも、自社にとってそれが必要かどうかは見極める必要があります。
カスタマイズ性や拡張性に優れたものを選ぶ
部品管理システムは一度導入すれば長期間にわたり使い続けることが多いため、導入時点だけでなく「将来的な業務の変化にも柔軟に対応できるか」といったカスタマイズ性・拡張性が大きな選定基準になります。具体的には、以下のようなものが拡張性のポイントです。
- 項目の追加・変更が自社でできるか
- ユーザーや部門ごとに表示項目・画面レイアウトを変更できるか
- 他システムとの連携機能(APIやCSV出力など)を標準で備えているか
- ワークフロー(承認フローや変更フロー)を柔軟に設計・修正できるか
- 将来的にライセンスや機能を段階的に追加できるか
部品管理システムでは、製品や業務内容の変化に応じて、入力項目の追加や既存項目の名称変更などのニーズが発生します。このとき、設定変更を自社で行えるかどうかは非常に重要です。ベンダーに都度依頼が必要な場合、コストや納期面で不利になる可能性があります。
現場・設計・調達などの部門や役職ごとに必要な情報は異なります。部品管理システム上で「誰にどの情報を表示するか」「見やすいレイアウトにカスタマイズできるか」は、使いやすさに直結するため、役割に応じた表示調整ができる仕組みは非常に有用です。
将来的にERP・PLM・MESなどの他システムと連携する可能性があれば、APIやCSV入出力などのデータ連携機能があるかを確認しましょう。最初は単独で使っても、業務が拡張される中でシステム間の情報共有が必要になるケースは少なくありません。
設計変更や部品追加など、業務には承認が必要な場面が多くあります。ワークフローが自由に設定・変更できるシステムであれば、組織変更や運用ルールの変化にも柔軟に対応可能です。逆に固定的な承認フローしか設定できないと、業務に支障をきたす恐れがあります。
導入当初は小規模でも、将来的にユーザー数や製品ラインが増える可能性があります。段階的にライセンスや機能を追加できるスケーラビリティがあるシステムであれば、コストを抑えつつ成長に合わせた拡張が可能です。
操作性がよく使いやすいものを選ぶ
いくら高機能な部品管理システムでも、現場で実際に使ってもらえなければ意味がありません。部品管理システムは、設計者やエンジニアだけでなく、調達・製造・品質管理・営業・保守サービスなど、社内の多部門が横断的に利用します。そのため、ITに慣れていないユーザーでも直感的に操作できるUIが求められます。
製造現場では、タブレットやスマートフォンでの表示対応や、図面や写真をすぐに確認できるビューア機能、バーコード読み取りによる検索補助など、使い勝手が業務効率に直結します。操作が複雑だと導入教育やマニュアル整備にも工数がかかり、初期コストや運用負荷も増加するため注意が必要です。
可能であれば、無料トライアルや実機デモを通して、実際にシステムを使う担当者が迷わず操作できるか、ストレスなく使えそうかを事前に検証しましょう。
セキュリティ・アクセス管理機能があるものを選ぶ
部品管理システムには製品の設計情報・調達条件・製造構成など、企業にとって機密度の高い情報が多く含まれます。そのため、アクセス権限管理と情報の保護機能は非常に重要です。
例えば、設計者にはBOMの編集権限を、製造部門には閲覧のみ許可するといった操作レベルでの権限制御が必要不可欠だといえます。また、部門やプロジェクト単位でアクセスできる範囲を制限し、不要な情報閲覧を防ぐことも求められます。
さらに、誰がいつどの情報にアクセス・変更したかを記録する操作ログ(監査ログ)機能も必要です。操作ログ機能を活用すれば、万が一のトラブル発生時にも、操作履歴の追跡ができます。
近年では、外部の協力会社やサプライヤーと一時的に情報を共有するケースも増えており、期限付きのアクセスやダウンロード制限といったセキュリティ機能も重視されるようになっています。
システム選定の際には、「どこまで細かく権限設定できるか」「社内外ユーザーをどう制御できるか」を具体的に確認しましょう。
コストや導入サポートを考慮して選ぶ
初期費用や月額利用料といったコストも、部品管理システム選定の大切なポイントです。導入目的を明確化し、導入の費用対効果を予測したうえで、無理のないコストで導入できるシステムを選定しましょう。
ただし、初期費用と月額利用料だけでシステムを選ぶのはリスクがあります。導入後のサポート体制やトラブル対応サービス、機能追加・仕様変更などのカスタマイズにどれだけの追加コストがかかるのかチェックが必要です。
特に部品管理システムは企業のコア業務に深く関わるため、導入後の疑問やトラブルへの対応がスムーズに行えるかどうかは、長期的な運用の安定性に直結します。また、操作教育やマニュアルの提供、初期設定支援などが手厚いベンダーであれば、導入がスムーズに進むでしょう。
将来的な機能追加や仕様変更、他システムとの連携ニーズが出てきた場合、都度高額なカスタマイズ費用がかかると、運用コストが膨らみやすくなります。目先のコストだけにとらわれず、導入サポート・運用支援・将来の拡張性まで含めて、トータルでの費用対効果を見極めましょう。
自社に合う提供形態のものを選ぶ
クラウド型・オンプレミス型という提供形態の違いも、重要な選定ポイントです。
クラウド型は、インターネット経由でサービスを利用する形式で、サーバーの購入・管理が不要なため、導入のハードルが低く、月額課金制で初期コストも抑えられるのが特長です。
インストール不要で複数拠点や自宅などからもアクセス可能なため、テレワークや多拠点展開を行っている企業に向いています。また、ベンダー側で自動的にシステムをアップデートしてくれるため、常に最新状態で利用できるのも魅力です。
一方で、「オンプレミス型」は自社内のサーバーにシステムを構築して運用する形式で、セキュリティ性の高さとカスタマイズの柔軟さが魅力です。特に自社独自のワークフローがある企業や、情報漏洩リスクを最大限に抑えたい業種(防衛産業や医療機器、重要インフラ関連など)では今でもオンプレミス型が選ばれるケースもあります。
まとめ
本記事では、部品管理の重要性や部品管理システムの機能・選び方などについて解説しました。部品管理は、製造業において製造工程全体をスムーズに進め、最適化するために重要な業務です。
適切な部品管理を効率的に行うためには、部品管理システムの導入が有効です。自社の抱えている課題などから導入目的を明確化し、予算内で必要な機能を網羅したシステムを選定して導入しましょう。
製品紹介
効率的な部品管理には、あらゆる部品情報の可視化と共有が必要不可欠です。これには、PIM(商品情報管理)システムが応用できます。部品管理システムと連携して、より効果的な部品管理を目指すなら、商品情報管理システム「KOKONIDAS(ココニダス)」がおすすめです。
部品管理に使っているシステムとKOKONIDASを連携すれば、各部品の品番・用途・入出庫履歴・単価・仕入先といった部品情報を一括管理できます。情報はリアルタイムに更新され、権限のある社内関係者がチェック可能です。
KOKONIDASでは、部品を管理する拠点や部門が複数ある場合にも、情報をまとめて管理可能です。また、管理しているデータは抽出して各種計画のための分析にも活用できます。
<KOKONIDASの特徴>
- リーズナブルなコストで気軽に導入できる
- システムの知識は不要で、誰でも簡単に操作できる
- パッケージ化されているため、早期運用開始ができる
KOKONIDASの詳しい機能や特徴はこちら
KOKONIDASはデモ環境での無料体験もご利用いただけます。部品管理システムとPIMを連携した部品管理の効率化を検討中の担当者様は、ぜひお気軽にお問い合せください。
KOKONIDASに関するお問い合わせはこちら