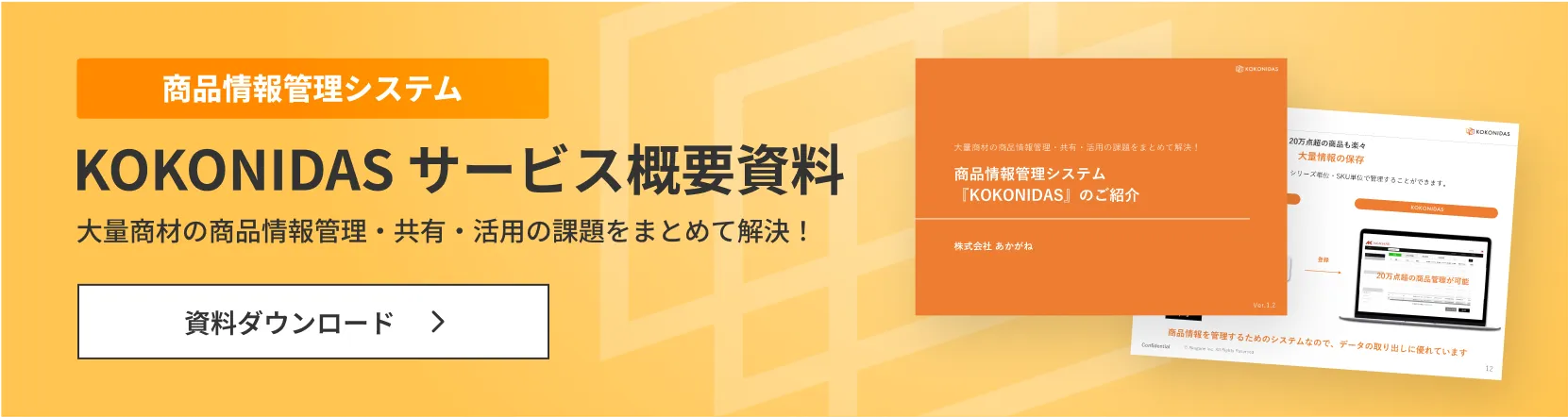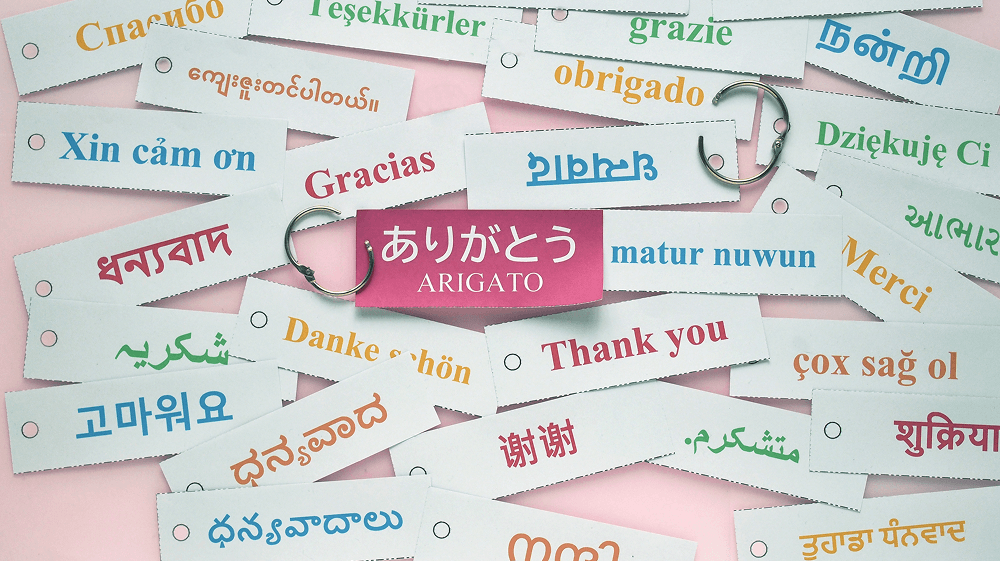記事公開日
最終更新日
製造業のデジタル化とは?メリットや進めるポイントを解説

製造業のデジタル化は、生産性向上や競争力の強化に欠かせません。IoTやAI、クラウドといったデジタル技術を活用すれば、スマートファクトリーも実現できます。
「まずは製造業におけるデジタル化とは何かを理解したい」「デジタル化のメリットを知りたい」といった担当者の方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、製造業におけるデジタル化とは何か、メリットや進めるためのポイントなどを解説します。デジタル化の例も紹介するので、自社のデジタル化を検討中の方はぜひ参考にしてください。
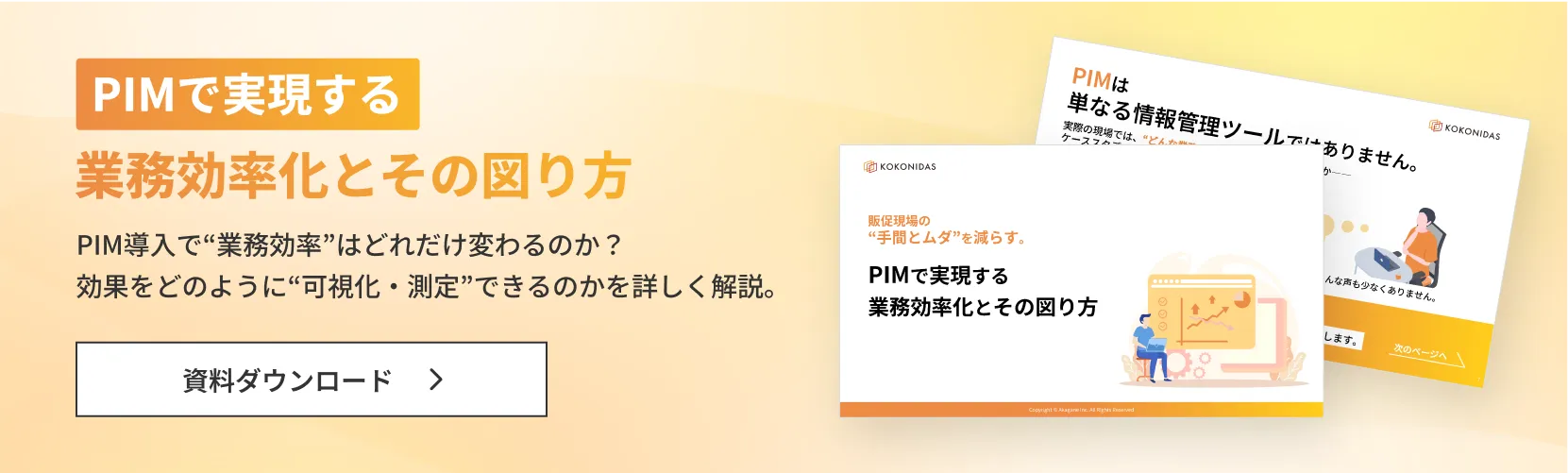
製造業のデジタル化とは?
製造業のデジタル化とは、工場や製造工程において、ITやデジタル技術を活用して業務を効率化・高度化する取り組みのことです。具体的には、IoT(モノのインターネット)・AI、ビッグデータ・クラウド・デジタルツインなどのテクノロジーを活用し、生産管理や品質管理・在庫管理・設備保守といった業務を自動化していくことが含まれます。
これまで、製造現場では経験則に基づいた属人的な業務が多く存在していました。しかし、競争の激化や人材不足、働き方改革による業務効率化の必要性などを背景に、デジタル技術の導入が急速に進みつつあります。
製造業が直面している課題
デジタル化は製造業が直面しているさまざまな課題の解決に役立ちます。
それぞれの課題について解説します。
人材不足や高齢化
日本の製造業では、深刻な人材不足と熟練工の高齢化が進んでいます。特に地方の中小企業では若年層の採用が困難で、現場を支えるベテラン技術者の引退により、長年蓄積されたノウハウや技能の継承が滞るケースも増加しています。
人材不足の問題は、単に労働力の確保だけでなく、品質の維持や生産性にも直結する深刻な経営課題となっており、早期の対応が求められています。デジタル化は、技術の標準化や作業の自動化を通じて、人に依存した構造を改善するための手段として注目されています。
グローバル競争の激化
近年、製造業を取り巻く市場環境はグローバル化の進展により、かつてないほど競争が激化しています。新興国企業の台頭や海外企業との価格競争により、品質やコスト、納期といったあらゆる面で高いレベルの対応が求められているのが現状です。
特にアジア地域では、デジタル技術を積極的に取り入れたスマートファクトリーの展開が進んでおり、従来のやり方では太刀打ちできない場面が増えています。競争力を維持・強化するためには、デジタル技術を活用した迅速かつ高品質なものづくりへの変革が急務です。
属人的な業務とデータの分断
多くの製造現場では、長年にわたり個々の作業員の経験や勘に依存した属人的な業務が根付いています。例えば、不良品の判断や設備の微調整などが特定のベテランにしかできないといったケースは珍しくありません。
また、現場での情報が紙やホワイトボード、Excelなどで個別に管理される例も多く見られます。こうした現場と管理部門、営業部門などとの間で情報がスムーズに連携できていないデータの分断も大きな課題です。
デジタル化は、こうした情報の一元管理や業務の標準化、作業の自動化を通じて、属人的な体制の改善にも役立ちます。
デジタル人材の不足
製造業においてデジタル化を推進する上で深刻な課題となっているのが、デジタル人材の不足です。
IoT・AI・クラウド・データ分析などの技術を活用するには専門人材が不可欠ですが、そうした人材は市場でも希少で、他業種との人材獲得競争が激化しています。特に中小企業では、自社内にIT人材を育成・確保するリソースが不足しており、導入したシステムを有効に活用できないケースも少なくありません。
また、現場とITの橋渡しができるデジタルと製造の双方の視点を持つ人材は貴重で、今後の競争力を左右する存在ともいえます。このような背景から、外部パートナーの活用や社内教育体制の整備が急務といえるでしょう。
製造業のデジタル化によって得られるメリット
製造業のデジタル化によって得られる代表的なメリットは以下の5つです。
それぞれのメリットについて解説します。
生産性の向上
製造業におけるデジタル化のメリットのひとつは、生産性向上です。IoTやセンサーによって工場内の設備稼働状況をリアルタイムで把握し、データ分析を通じて生産ラインのボトルネックや非効率な工程を特定することが可能になります。
これにより、稼働率の改善・段取りの最適化・工程間の無駄の排除といった改善が実現します。さらに、AIを活用した生産計画の自動立案や、需要予測に基づいた資材手配なども精度が高まり、生産の無駄の減少も期待できるでしょう。
人材不足の解消
製造業では、技術者の高齢化や若年層の入職率低下により、深刻な人手不足が問題となっています。デジタル化はこうした課題の解消にも大きく貢献します。
例えば、ベテランの経験や判断に頼っていた作業をデータ化・標準化することで、特定の個人に依存せず、誰でも一定の品質で作業ができる環境を整えることが可能です。また、業務の一部を自動化・省人化すれば、限られた人員でも効率的に製造が可能になります。
業務負担の軽減
製造現場や事務部門において、手作業によるデータ入力・設備の巡回確認・帳票の作成・管理といった業務が多く、従業員に大きな負担をかけているケースが少なくありません。デジタル化によってこれらの業務を自動化・効率化することで、現場の負担を大幅に軽減することが可能になります。
例えば、IoTセンサーを活用すれば、設備の状態や異常を自動で記録・通知できるため、巡回作業や手書き記録の手間がなくなります。さらに、受発注処理や在庫管理などのルーチン業務も自動化すれば、社員はより創造的・戦略的な業務に集中できるようになります。
コスト削減
製造業におけるデジタル化は、さまざまなコストの削減にも直結します。
まず、IoTやAIを活用することで、設備の稼働率向上やエネルギー使用の最適化が図れるため、電力や稼働コストの削減が可能です。また、予知保全の仕組みにより設備の故障や突発的な停止を未然に防ぐことで、メンテナンス費用や生産ロスを大幅に抑えることができます。
さらに、在庫の最適化により不要な保管コストを削減でき、資材の発注の無駄も減少します。クラウドシステムなどによって事務作業の効率化が進めば、人件費の抑制にもつながるでしょう。
品質向上
製造業において、品質の安定と向上は企業の信頼を守るために欠かせません。
デジタル化により、製造過程で発生するデータをリアルタイムに収集・分析することで、品質に影響を与える要因を即座に特定・制御できるようになります。これにより、不良品の発生を未然に防ぐことができ、安定した品質で製品を提供することが可能です。
また、検査工程の自動化やAIによる画像認識などを導入すれば、人の判断に頼ることなく、精度の高い検査が実現します。さらに、トレーサビリティが強化されることで、万が一の品質トラブルにも迅速かつ正確に対応でき、信頼回復や再発防止につながるでしょう。
製造業のデジタル化の例
製造業のデジタル化に関する例を3つ紹介します。
事例①:IoTを活用したスマートファクトリーの実現
ある自動車部品メーカーでは、新たに稼働した生産ラインにおいて、IoT技術を駆使したスマートファクトリーを導入しました。
具体的には、工作機械やセンサーなどの制御機器から稼働データや消費電力を収集し、リアルタイムで可視化するシステムを構築しました。これにより、設備の異常兆候を早期に検知し、予知保全を可能にしています。
また、製造現場の状況はモバイル通信を通じてクラウド上に集約され、遠隔地からでも生産状況の監視・管理が可能です。結果として、機械の故障リスクを大幅に低減しつつ、稼働率の向上や保守業務の効率化も実現しました。スマートファクトリーの好事例として、他の工場への展開も検討されています。
事例②:デジタルツイン技術による生産シミュレーション
ある総合電機メーカーは、生産工程の効率化とリスク回避を目的に、デジタルツイン技術を活用した生産シミュレーションを導入しています。これは、実際の工場の設備やレイアウトをデジタル上に再現し、現場と同じデータをリアルタイムで仮想空間に反映させる技術です。
これにより、新たなライン構築や設備変更の前に、さまざまなシナリオを仮想上で検証することが可能となり、トラブルやムダを事前に排除できます。また、既存の工程においてもボトルネックの把握や稼働バランスの最適化が可能となり、全体の生産効率が向上しました。
この技術は、省人化やスピーディーな意思決定にも貢献しており、同社では今後の生産戦略の中核技術として位置づけています。
事例③:工場間連携による生産効率の向上
ある電子機器メーカーでは、複数の工場で同じ部品を使用していたにもかかわらず、それぞれで仕様や生産方法が異なっており、調達コストや管理工数が増大していました。
これに対し、設計や生産におけるデータを統合・共通化し、異なる工場を仮想的に1つの製造拠点として機能させる仕組みを構築しました。生産スケジュールや在庫管理も一元化され、需要変動にも柔軟に対応できるようになりました。
結果として、生産性の向上だけでなく、在庫削減や納期短縮といった効果も現れています。また、設計情報の再利用が可能となったことで、製品開発のスピードも加速しました。この取り組みは、業務標準化と柔軟な製造体制の両立を目指す好例といえるでしょう。
製造業のデジタル化を進めるためのポイント
製造業のデジタル化を進めるための主なポイントは、以下の3点です。
それぞれのポイントについて解説します。
解決する課題を設定する
デジタル化を進める前に、まずは自社が抱える本質的な課題を明確にしましょう。例えば「不良品が多い」「残業が多い」「在庫が過剰」「設備の稼働率が低い」など、現場で感じている困りごとを洗い出し、その中で優先順位の高いものから着手します。
課題を定量的に測定できるようにすれば、デジタル施策の効果も可視化しやすくなり、社内の理解と納得も得られやすくなります。課題があいまいなままでは、システムを導入しても期待する効果が得られず、現場との乖離が生じる原因となるため要注意です。
DX人材を確保する
デジタル化を推進するためには、ITやデータ分析に強い専門人材の確保が欠かせません。業務プロセスの可視化やシステム導入、データ活用の仕組みづくりなど、従来の製造スキルとは異なるノウハウが求められます。
しかし、こうした人材は市場でも希少であり、採用や育成が困難なケースもあります。そのため、社内育成と並行して、外部のDXコンサルティング会社やITベンダーと連携しながらプロジェクトを進めることも有効です。
また、現場の稼働状況や業務実績をデータとして記録・蓄積していく体制を整えましょう。蓄積されたデータを分析すれば、業務改善に活用できます。
小規模な施策から取り組み始める
製造業におけるデジタル化は、いきなり全社的な大規模改革を行うのではなく、小さな範囲から段階的に進めるのが現実的です。例えば、まず1台の設備にセンサーを取り付けて稼働状況を可視化する、あるいは特定の事務作業に導入してみるといったスモールスタートを計画しましょう。
小規模なデジタル化で効果や課題を評価し、改善しながら適用範囲を広げて行きます。長期的な導入計画を策定し、費用対効果を確認しながら最終的な全社展開を目指しましょう。
まとめ
本記事では、製造業におけるデジタル化とは何か、製造業が直面している課題と紐づけて解説しました。デジタル化は、生産性の向上や人材不足の解消、コスト削減などさまざまなメリットをもたらします。
グローバル競争の激化へ対応するためにも、製造現場のデジタル化は必要不可欠です。国内の企業にも、業務をデジタル化して生産性向上などを実現した事例が数多くあります。
デジタル化を進める場面では、デジタル化によって解決したい課題の明確化が大切です。また、デジタル技術に詳しい人材の確保も求められます。人材確保が難しい場合は、外部のベンダーなどのサポートを受けるとよいでしょう。
まずは小規模なデジタル化で費用対効果や課題を評価しながら、全社に展開していくことをおすすめします。
製品紹介
製造現場のデジタル化には、製品・部品・原料などに関するさまざまな情報を可視化し、どこからでも閲覧できるようにしておく必要があります。こうしたさまざまなデータの可視化と共有には、PIM(商品情報管理)システムが応用できます。IoT化に活用するPIMシステムなら、商品情報管理システム「KOKONIDAS(ココニダス)」がおすすめです。
KOKONIDASでは、自社の製品はもちろん、その部品や原料に関する情報などもまとめて一元管理できます。情報はリアルタイムに更新され、権限のある社内関係者がチェック可能です。
<KOKONIDASの特徴>
- リーズナブルなコストで気軽に導入できる
- システムの知識は不要で、誰でも簡単に操作できる
- パッケージ化されているため、早期運用開始ができる
KOKONIDASの詳しい機能や特徴はこちら
KOKONIDASはデモ環境での無料体験もご利用いただけます。現場のデジタル化に向けたPIMシステムの導入を検討中の担当者様は、ぜひお気軽にお問い合せください。
KOKONIDASに関するお問い合わせはこちら