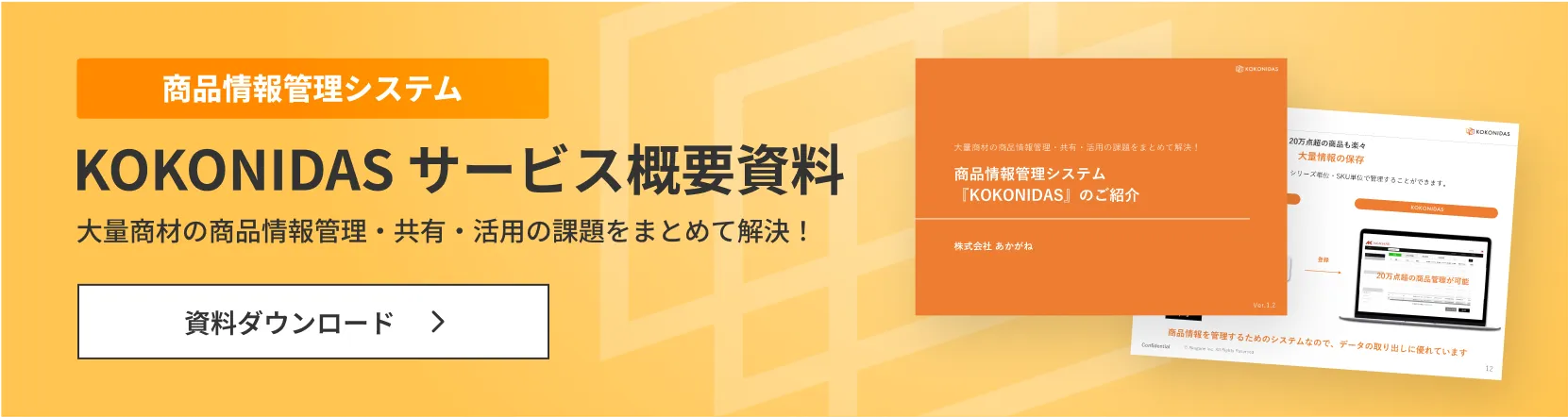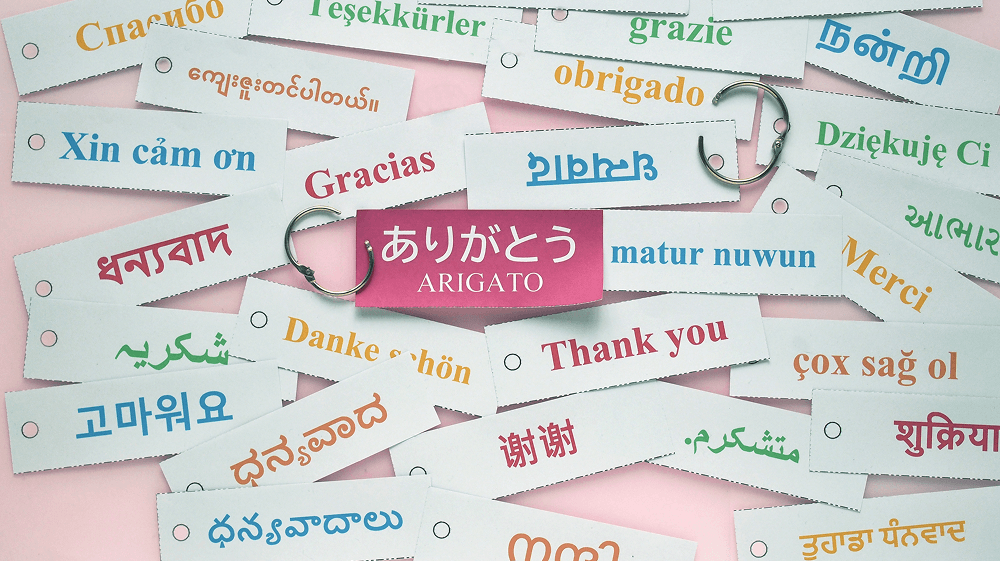記事公開日
最終更新日
PDM(製品情報管理)システムとは?導入するメリットや注意点を解説

PDM(製品情報管理)システムは、自社製品の設計や開発などに関連する図面・部品情報といった情報を一元管理するシステムです
社内に分散している情報を1つのシステムにまとめることで、業務効率の向上やセキュリティ強化などが見込めます。
とはいえ、PDMシステムの導入には手間とコストがかかるため、「PDMシステムの導入メリットをより詳しく知りたい」「PDMシステム導入時の注意点を確認したい」といった方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、PDMシステムとは何か、主な機能や導入のメリットなどを解説します。
PDMシステム導入時の注意点やポイント、製品情報の一元管理に役立つシステムなども紹介するため、ぜひ最後までチェックしてみてください。
これを読めば、PDMシステムとは何かを理解でき、自社の製品情報管理が抱える課題を解決するためのヒントが得られるでしょう。
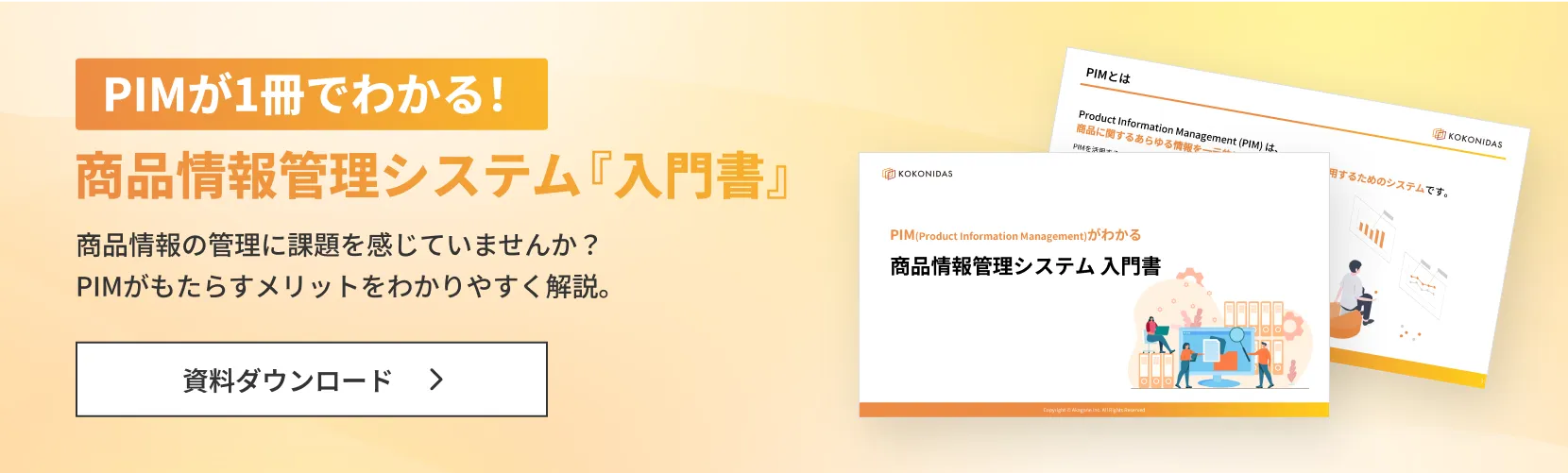
PDM(製品情報管理)システムとは
PDM(Product Data Management:製品情報管理)システムとは、製造業における設計・開発・生産・保守・管理といった製品の情報を一元管理するためのシステムのことです。
PDMシステムでは、主に以下のような情報を管理します。
<PDMシステムが管理する情報例>
| 管理する情報 | 内容例 |
|---|---|
| 製品情報 | 製品名・型番・バージョン・BOM(部品表)など |
| 図面・CADデータ | 2D/3D設計データ・仕様書など |
| 設計履歴 | バージョン管理・設計変更履歴・承認記録など |
| 部品情報 | 使用部材・ロット情報・代替品など |
| ドキュメント | マニュアル・検査表・関連報告書など |
PDMシステムで一元管理する情報は、設計部門以外のさまざまな部門が閲覧でき、スムーズな情報共有ができるようになります。
PDMとPLM、PIMなどとの違い
PDM(製品情報管理)と似たものにPLM(Product Lifecycle Management:製品ライフサイクル管理)とPIM(Product Information Management:商品情報管理)があります。
どれも製品の情報を一元管理する点では共通していますが、用途や管理対象が異なる別のシステムです。
<PDM・PLM・PIMの違い>
| 項目 | PDM(製品情報管理) | PLM(製品ライフサイクル管理) | PIM(商品情報管理) |
|---|---|---|---|
| 目的 | 技術データの管理/共有 | 製品開発の最適化 | 商品情報の統一と一元管理 |
| 管理対象 | 図面・BOM・設計データなど | 開発スケジュール・品質データ・承認フローなどライフサイクル全体の情報 | スペック・画像・説明文・商品カテゴリなど |
| 主な使用部門 | 設計・製造 | 全社 | マーケティング・販促 |
| 主な使用分野 | 製造業 | 製造業 | 小売業 |
PLM(製品ライフサイクル管理)では、開発〜販売までの製品ライフサイクル全体のあらゆる情報を管理します。
管理する情報は全社で共有され、活用目的は製品開発の最適化です。
PDMが管理する情報はPLMが管理する情報の一部にあたります。
PIM(商品情報管理)は、商品のスペックや画像といった販促活動に必要な商品情報を一元管理するシステムです。
主に小売業やECサイトを運営する企業のマーケティングや販促を行う部門が活用します。
PDM(製品情報管理)システムの主な機能
PDM(製品情報管理)システムの主な機能は以下の4つです。
- データ管理機能
- ワークフロー管理機能
- 検索機能
- セキュリティ機能
それぞれの機能で何ができるのかチェックしておきましょう。
データ管理機能
データ管理機能は、PDM(製品情報管理)システムの中核となる機能です。
図面・仕様書・BOM・CADファイルなど製品の設計に関連するあらゆる情報を一元管理します。
PDMのデータ管理機能では、バージョン管理やリビジョン管理も可能です。
設計データの変更履歴を追跡したり、同一製品の情報の改訂版をリビジョンごとに整理したりできます。
これにより利用者は最新版の設計資料へのアクセスが容易になり、誤ったデータを元に製造してしまうリスクを低減できます。
データ管理機能で扱う情報は、品番・設計者・日付・用途などの属性も設定可能です。
また、CADデータや仕様書を他のデータと紐付けられるファイルリンク機能も備えているため、必要な情報に辿り着きやすいのも特徴です。
<データ管理機能の例>
| 機能 | 内容 |
|---|---|
| バージョン管理 | 図面や設計データの変更履歴(いつ・誰が・何を)を記録 |
| リビジョン管理 | 同一製品の改訂履歴を記録 |
| 属性管理 | 品番・設計者・日付・製品用途などの属性データの紐付けて管理 |
| ファイルリンク | CADデータ・仕様書などを他のデータと紐づけて管理 |
ワークフロー管理機能
PDM(製品情報管理)システム上に設計情報をリリースしたり、登録している情報を編集したりする際の申請・承認のステップは、ワークフロー管理機能によって実施できます。
承認フローを電子化することで抜け漏れをなくし、最新情報をスピーディに共有可能です。
ワークフローの進捗状況はシステム上で確認でき、承認の通知を受け取れるものもあります。
承認者などは組織に合わせて自由に設定できるものが一般的です。
検索機能
PDM(製品情報管理)システムには、管理している膨大な情報の中から必要な情報を見つけるための検索機能が備わっています。
検索機能の充実度はシステムによって異なるため、自社の使い方に適した検索機能を備えたシステムを採用しましょう。
製品名や品番のほかに、属性やBOMなどから逆引き検索が可能です。
システムによっては、登録しているファイル内の文言で検索できるものもあります。
セキュリティ機能
PDM(製品情報管理)システムで扱う情報は機密性が高いため、各システムが不正アクセスや情報漏洩、誤操作による意図しない情報の更新などを防ぐためのセキュリティ機能を備えています。
主なセキュリティ機能は以下のとおりです。
<PDMのセキュリティ機能の例>
| セキュリティ機能 | 内容 |
|---|---|
| アクセス権限管理 | 部署やユーザーごとに閲覧・編集などの権限を設定できる |
| ログ管理 | いつ誰が閲覧・編集したのかを記録できる |
| 外部アクセス制限 | VPNやファイル暗号化などを利用して外部からのアクセスを制限できる |
アクセス権限管理機能では、部署単位やユーザー単位で閲覧・編集といったアクセス権限を設定できます。
不要な人に権限を与えないことで、情報漏洩や誤操作による意図しない編集のリスクを抑えられるでしょう。
仮に不自然な編集の跡が見つかったとしても、ログ管理機能を使えば、いつ誰が編集したのかを追跡可能です。
ログ管理機能は、製品情報に誤りが見つかった際の原因特定や再発防止に役立ちます。
PDMシステムでは、外部からのアクセス制限も可能です。
例えば、海外拠点やテレワーク中の端末などからのアクセスを必要最低限にしておけば、情報漏洩リスクを低減できるでしょう。
PDM(製品情報管理)システムの導入メリット
PDM(製品情報管理)システムの導入には、さまざまなメリットがあります。
主な導入メリットは、以下の5点です。
- データを一元管理できる
- リアルタイムで情報共有ができる
- 業務プロセスを標準化できる
- 生産性を向上できる
- セキュリティを強化できる
それぞれのメリットをチェックしてみましょう。
データを一元管理できる
自社製品の設計に関わるデータを一元管理できるのは、PDM(製品情報管理)システム導入の一番のメリットです。
これまで社内に分散していたデータをPDMに集約して管理することで、データの検索・編集・更新などが容易に行えるようになります。
変更履歴やリビジョンが整理できる点もポイントです。
情報が分散している状態では最新版のデータにたどり着くのに時間がかかりますが、PDMシステムで管理していれば過去バージョン含め追跡が容易です。
リアルタイムで情報共有ができる
PDM(製品情報管理)システム上で更新された情報は、設定した承認フローを経て全社にリリースされます。
各部署が常に最新の情報にアクセスできるようになることで、誤ったデータを元にした製造や部材発注を防止可能です。
PDM(製品情報管理)システム上の最新データは、どこからでも閲覧できます。
海外拠点との連携やテレワーク社員が多い企業においても、効率的にリアルタイムの情報を共有できるでしょう。
業務プロセスを標準化できる
PDM(製品情報管理)システムでは、情報の更新からリリースまでのワークフローを設定できるため、設計情報更新の業務プロセスを標準化できます。
人によって違う方法でデータを更新するよりも、均一化された使いやすいデータとして管理できるでしょう。
ワークフロー設定による業務プロセスの標準化は、承認漏れや誤った情報が公開されるリスクの低減にも役立ちます。
結果として内部統制が強化されるといえるでしょう。
生産性を向上できる
PDM(製品情報管理)システムの導入は、さまざまな面で生産性を向上します。
製品情報を一元管理することでデータの二次利用がしやすくなります。
資産でもある過去の設計データを、次の開発や設計に活かすことが可能です。
参考にしたいデータを探す時間が短縮できるのも、生産性向上につながります。
例えば、他部署が保有する情報を入手するのに時間がかかっていた場合でも、PDMシステムを導入すれば、システム上で検索するだけで簡単に手に入るでしょう。
セキュリティを強化できる
セキュリティ強化にもPDM(製品情報管理)システムの導入は効果的です。
PDMではアクセス権限設定やログの記録ができるため、各部署が個別のルールで情報を保管している状態と比べるとセキュリティ性は高いといえます。
不正アクセスによる情報漏洩や誤操作による意図しない編集が生じた場合でも、PDMシステム上で情報を管理していれば、原因を特定できる可能性があるでしょう。
PDM(製品情報管理)導入時の注意点・ポイント
PDM(製品情報管理)導入時の注意点やポイントを解説します。
主な注意点・ポイントは以下の3つです。
- 導入する目的を明確にする
- 全社で取り組む
- 段階的に導入する
- 費用対効果を検証する
それぞれ詳細をチェックしておきましょう。
導入する目的を明確にする
PDM(製品情報管理)システムの導入を検討する場合は、まず導入目的を明確化しましょう。
目的が曖昧なままシステム導入の検討を進めると、自社に合わないPDMシステムを選んでしまう可能性があるため注意しましょう。
導入目的の明確化は、自社内でのデータ管理の現状を把握し、課題を抽出するとスムーズです。
例えば、PDMシステムの導入が望ましい企業の現状としては、以下のようなものが挙げられます
- 設計データや図面がバラバラに管理されており、最新版がどれなのかわからない
- 設計変更の承認フローや履歴管理の属人化により、伝達漏れやミスが発生している
- 部門間での情報共有がうまくいかず、手戻りが発生している
こうした現状の課題がある場合は、その解決を目的として導入するPDMシステムを選定しましょう。
PDMシステムにもそれぞれ特徴があるため、自社の課題解決に効果的な機能・強みを持ったシステムを採用する必要があります。
全社で取り組む
社内全体のデータ管理方法に関わるPDM(製品情報管理)システムの導入は、全社で取り組むのが望ましいでしょう。
経営陣だけで取り組むと現場が抱えている課題をうまく汲み取れない可能性もあるため要注意です。
PDMシステムの導入が決まったあとも、全社で連携する必要があります。
現場担当者と協力してシステムの運用体制を構築し、操作方法などのマニュアルを整備しましょう。
新しいシステムの導入は現場に負荷をかけるため、導入目的や見込まれる効果などをしっかり説明することも大切です。
段階的に導入する
PDM(製品情報管理)システムの導入は、段階的に進めましょう。
PDMシステムを導入すると、更新時のワークフローが複雑化したり、管理する情報が増えたりと現場の担当者に負荷がかかる場合があります。
最初から全社に導入すると、システムの活用自体が困難になる可能性もあるため要注意です。
まずは特定の部署で導入を始め、現場からのフィードバックを受けながら全社への導入ステップを整えましょう。
ある程度運用効果が見られたら少しずつ全社に展開していきます。
情報に優先順位を付け、優先度の高い情報からPDM管理に切り替えるなどの工夫も効果的です。
費用対効果を検証する
製品情報を一元管理するPDM(製品情報管理)システムには、やや導入効果が評価しづらいという注意点があります。
運用を開始したら、導入によって改善した点などから費用対効果を検証しつつ、運用面で残る課題などを整理しましょう。
PDMシステムの導入後、かえって複雑化してしまった業務などがあれば、改善に取り組みます。
細かい運用体制やマニュアルは適宜改善しながら、自社の業務に適した製品情報の管理ができる環境を整えましょう。
まとめ
本記事では、PDM(製品情報管理)システムとは何か、具体的な機能や導入メリットなどを解説しました。
PDMシステムは、自社製品の主に設計に関わる情報を一元管理するシステムです。
PDMの導入メリットとしては、データの検索がしやすくなることによる業務効率向上や、アクセス権限設定などによるセキュリティ強化などが挙げられます。
更新情報もリアルタイムで共有できるため、どこからでも最新情報を参照できる点も大きなメリットです。
PDMシステムを導入する場合は、自社の課題に応じた導入目的の明確化が必要です。
導入が決まったら全社で協力し、システムの運用体制を整えましょう。
まずは一部の部署にのみ導入し、運用方法を改善しながら少しずつ全社に広げるのが効果的です。
製品紹介
PDM(製品情報管理)のようなシステムで自社製品の情報を一元管理したい場合には、商品情報管理システム「KOKONIDAS(ココニダス)」をご検討ください。
KOKONIDASは、さまざまな社内システムと連携して自社製品の情報を吸い上げ、社内各部署に共有できる形に一元管理できます。
KOKONIDASで管理する製品情報は、変更があるとリアルタイムに更新されます。
アクセス権限設定もできるため、社内の必要な人だけが必要な情報にアクセスできるセキュリティも確保可能です。
<KOKONIDASの特徴>
| 特徴 | 活用方法・課題解決 |
|---|---|
| 汎用的なデータ構造で、項目の追加・編集が可能 | 取引先からの商品情報データ提供依頼に対して、加工などの手間なく必要な情報を共有できる |
| 提供先のフォーマットに適したデータのアウトプット | 複数の販売チャネルやプラットフォームへのデータ出力時、個別にデータを作成する手間は不要 |
| システム開発不要なパッケージシステム | 導入が容易で費用も抑えられる |
| 充実のデータ制作支援 | 既存システムから情報を吸い上げてデータを制作・メンテナンスする作業のサポートを対応 |
KOKONIDASの詳しい機能や特徴はこちら
KOKONDASはデモ環境での無料体験もご利用いただけます。
在庫管理システムとPIMを連携した在庫管理の効率化を検討中の担当者様は、ぜひお気軽にお問い合せください。
KOKONIDASに関するお問い合わせはこちら